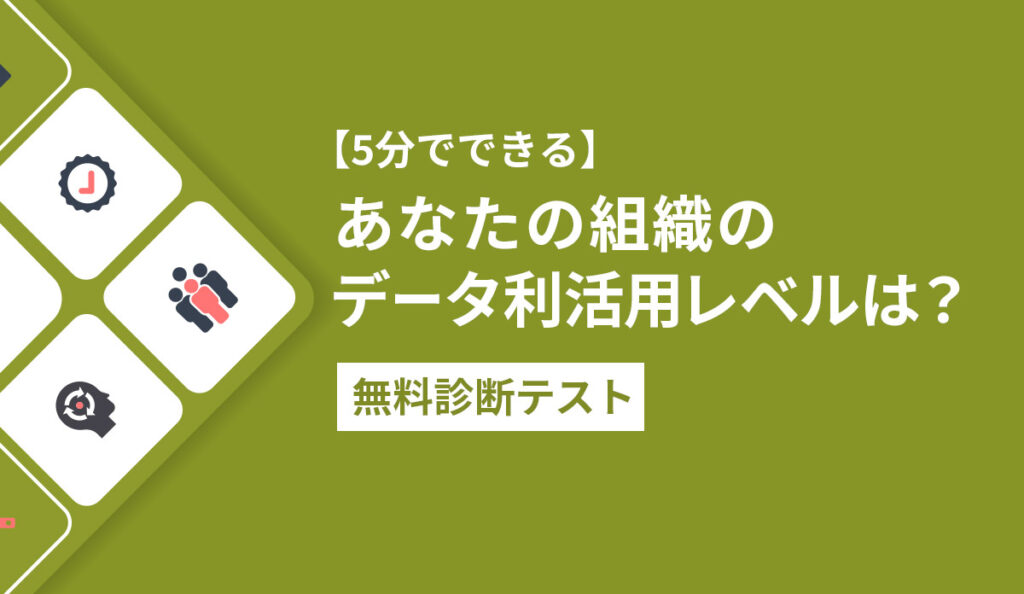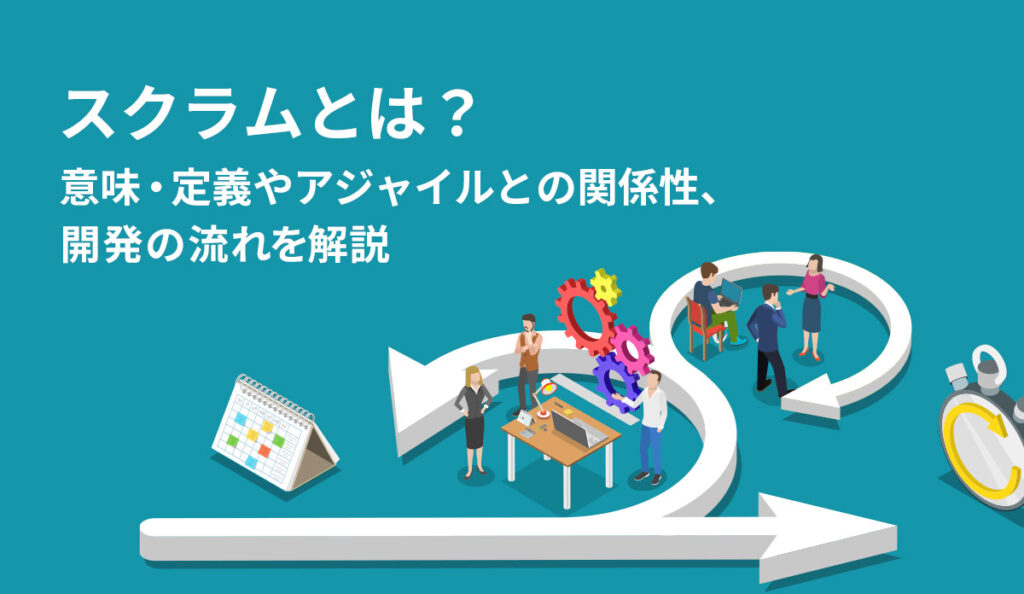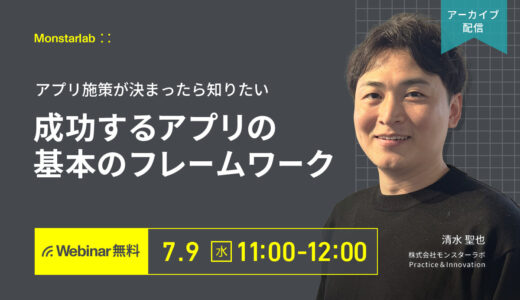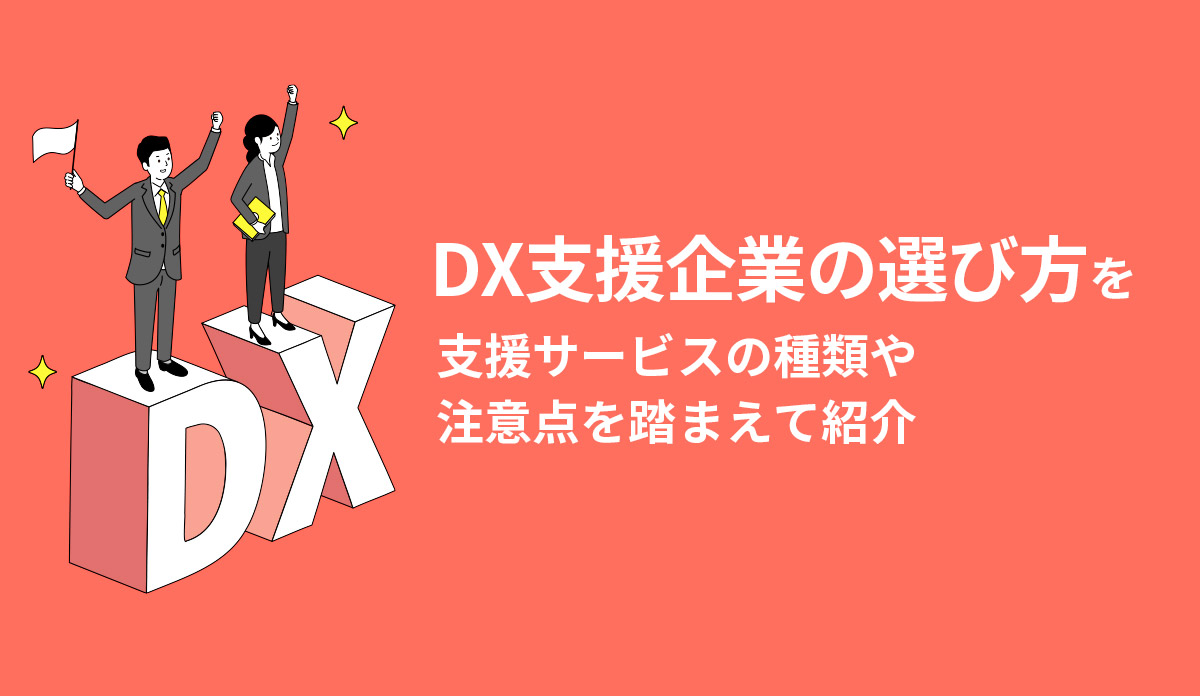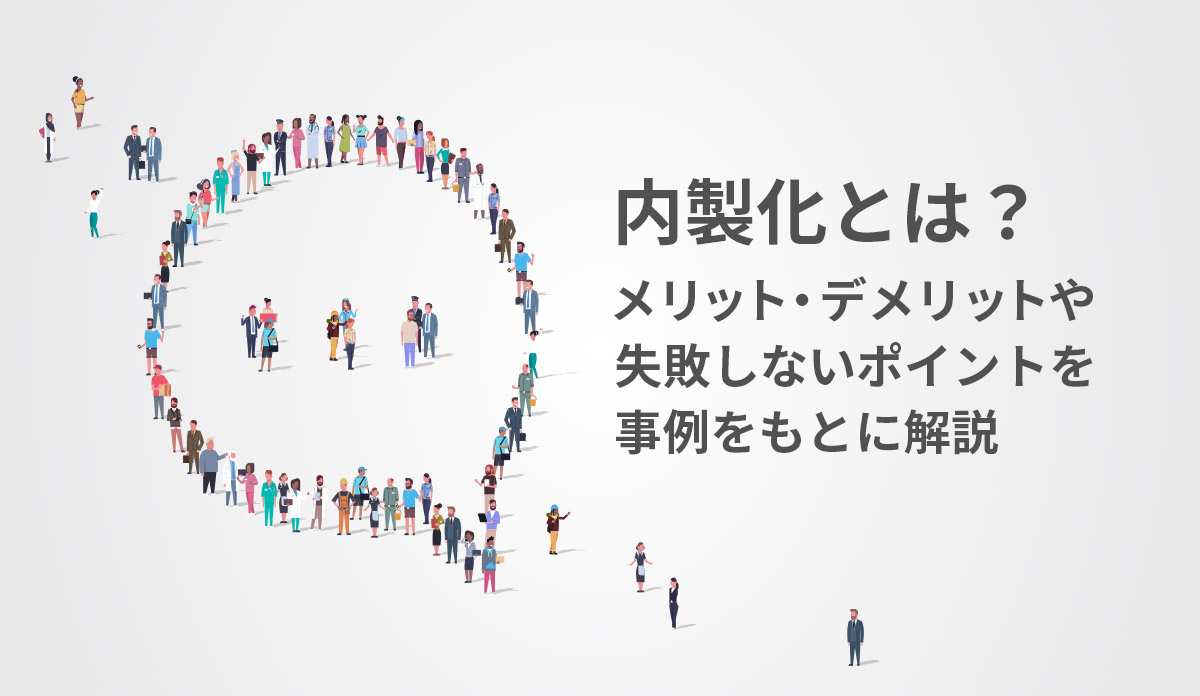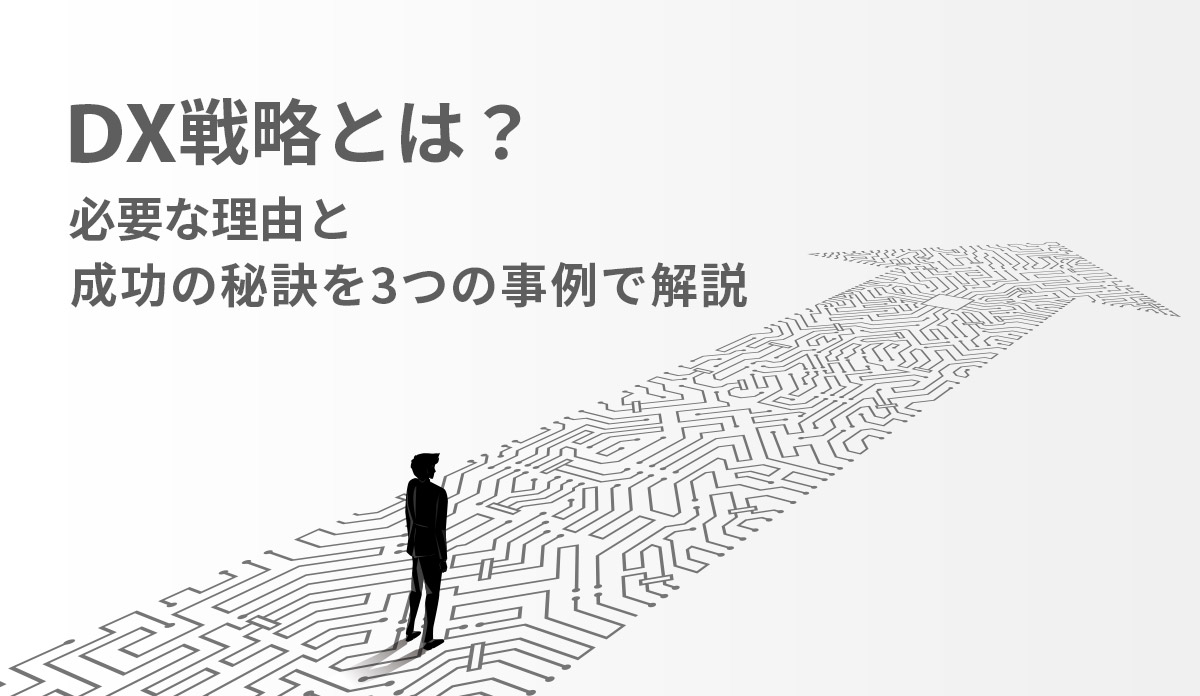本記事ではDX(Digital Transformation|デジタルトランスフォーメーション)についてわかりやすく解説。「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」との違い・関係性から、ビジネス領域で注目されている理由、日本企業におけるDX推進の現状と課題、先行事例まで簡潔に説明していきます。
➡︎【資料ダウンロード】さまざまな業界のDX推進事例をわかりやすく解説「DX事例集」<2025年版>
➡︎【資料ダウンロード】確実に進める生成AI活用の実践ガイド「LLM Loop導入支援」
目次
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?
「DX(デジタルトランスフォーメーション)」とは、企業がAI、IoT、ビッグデータなどのデジタル技術を用いて、業務フローの改善や新たなビジネスモデルの創出だけでなく、レガシーシステムからの脱却や企業風土の変革を実現させることを意味します。
DX推進はあらゆる企業にとって、変化の激しい時代のなかで市場における競争優位性を維持し続けるための重要なテーマです。
➡︎【資料ダウンロード】さまざまな業界のDX推進事例をわかりやすく解説「DX事例集」<2025年版>
➡︎【資料ダウンロード】確実に進める生成AI活用の実践ガイド「LLM Loop導入支援」
DXの本来の意味・定義
DXとは、デジタル技術を社会に浸透させて人々の生活をより良いものへと変革することを指します。
デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)の略で、直訳すると「デジタル変革」という意味になります。本来はビジネス領域に限った言葉ではなく、より広義な意味を持っています。
DXは2004年にスウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授によって提唱された概念で、その内容は「進化し続けるテクノロジーが人々の生活を豊かにしていく」というものでした。
ただし、DXが及ぼすのは単なる「変革」ではなく、デジタル技術による破壊的な変革を意味する「デジタル・ディスラプション」。すなわち、既存の価値観や枠組みを根底から覆すような革新的なイノベーションをもたらすものと定義されています。
➡︎【資料ダウンロード】さまざまな業界のDX推進事例をわかりやすく解説「DX事例集」<2025年版>
- デジタル技術を浸透させることで人々の生活をより良いものへと変革すること
- 既存の価値観や枠組みを根底から覆すような革新的なイノベーションをもたらすもの
DXとIT化の違い
デジタル化と同様に、DXと混同されることが多いのが「IT化」です。
ITはInformation Technologyの略であり、コンピューターとネットワーク技術の総称。インターネットやデジタルテクノロジーの進化に伴い、「旧来のアナログな作業をデジタル化して便利にする」という意味合いでIT化という言葉が使われるようになりました。
DXが社会や組織・ビジネスの仕組みそのものを変革することなのに対し、IT化は既存の業務プロセスのまま業務効率化と生産性向上を図るという非常に限定的な言葉です。
デジタル化と同様に、IT化もDX推進に向けた手段の1つでしかありません。
★「DX化」と「IT化」の違いについて詳しくはこちら
➡︎【資料ダウンロード】さまざまな業界のDX推進事例をわかりやすく解説「DX事例集」<2025年版>
DXレポートにみるDXトレンドの変遷
2018年に経済産業省が発表した『DXレポート』を皮切りに、DXは日本で広く知られる言葉となりました。この『DXレポート』で語られた「2025年の崖」問題が注目を集め、多くの企業が近い将来に直面する課題とDX推進の重要性を認識しました。
DXレポートは2018年から2023年現在まで計4回発表されていますが、時期を追うごとに日本企業が直面しているDX推進の課題が変化していく様子を窺い知ることができます。それぞれのレポートで語られた内容から、これまでのDXトレンドの変遷をおさらいしていきましょう。
➡︎【資料ダウンロード】さまざまな業界のDX推進事例をわかりやすく解説「DX事例集」<2024年版>
『DXレポート(2018年)』:「2025年の崖」への警鐘
2018年の『DXレポート』では「2025年の崖」問題に警鐘をならし、DXを推進しない場合に多くの企業が2025年を節目に直面する問題を示しました。
もしも対策をとることができず放置してしまった場合、大きく分けて下記の3つの問題に日本企業の多くが直面すると説明されています。
・既存基幹システムの老朽化に対して、デジタル市場の拡大とともに増大するデータ
・メインフレームの担い手の高齢化による世代交代の必要性
・テクノロジーの進化に伴う先端IT人材の不足
(出典)DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~/経済産業省
これらの状況に陥ってしまった場合、市場や環境のニーズの変化に柔軟に対応することができず、世界的に激化しているデジタル競争の敗者となってしまい、大きな経済的損失が生じてしまいます。また、老朽化したレガシーシステムを使い続けることによりシステム維持管理費用の高額化や担い手不足などの問題に対処できなくなる、セキュリティリスクが高まる、といった深刻なデメリットにも言及しています。
➡︎【資料ダウンロード】さまざまな業界のDX推進事例をわかりやすく解説「DX事例集」<2025年版>
『DXレポート2(2020年)』:DX=レガシー企業文化からの脱却
2020年に発表された『DXレポート2』では、コロナ禍によって社会全体でデジタル移行に拍車がかかるなかで企業文化も合わせて変革を図ることの重要性を強調し、企業が取るべきアクションや方向性を具体的にまとめています。
企業が市場競争力を身につけるためには、変化の激しい市場のニーズや、顧客、社会の課題をとらえ、素早く柔軟にビジネスを変革し続けることのできる俊敏性を身につけることが重要であるとしています。したがって、ITシステムに限らず、企業文化そのものを変革する必要があると指摘しています。
➡︎【資料ダウンロード】さまざまな業界のDX推進事例をわかりやすく解説「DX事例集」<2025年版>
『DXレポート2.1(2021年)』:ユーザー企業とベンダーの依存関係とジレンマ
2021年に発表された『DXレポート2.1』では、『DXレポート2』においてDX推進に必要と説明されていた「ユーザー企業とベンダー企業の共創」に関して、単純な「コスト削減」や「安定的なビジネスの享受」を目的とした両者の相互依存関係がデジタル産業への変革を阻むリスクと指摘しています。
また、こうしたジレンマを打破するためには、デジタル産業を構成する企業はデジタルを活用して価値を創出し、その価値を介して他社や顧客とつながるエコシステムを形成していく必要があることを示しました。
➡︎【資料ダウンロード】さまざまな業界のDX推進事例をわかりやすく解説「DX事例集」<2025年版>
『DXレポート2.2(2022年)』:デジタル産業への変革
2022年に発表された『DXレポート2.2』は、デジタル産業への変革に向けた具体的な方向や3つのアクションを示しています。
・デジタルを、省力化・効率化ではなく、収益向上にこそ活用すべきであること
・DX推進にあたって、経営者はビジョンや戦略だけではなく、「行動指針」を示すこと
・個社単独ではDXは困難であるため、経営者自らの「価値観」を外部へ発信し、同じ価値観をもつ同志を集めて、互いに変革を推進する新たな関係を構築すること
(出典)DXレポート2.2(概要)
➡︎【資料ダウンロード】さまざまな業界のDX推進事例をわかりやすく解説「DX事例集」<2025年版>
『DX動向2024』にみる取り組み状況と成果
日本企業のDX推進状況について、米国との比較や企業規模に合わせて分析されたレポート『DX動向2024』があります。IPAが2024年6月に発表したもので、これまでは『DX白書』という名称で発表されていました。2023年に発表された『DX白書2023』の内容を振り返りつつ、『DX動向2024』の概要を解説します。
『DX白書2023』:進まないトランスフォーメーション
IPAが2023年2月に発表した『DX白書2023』の内容を「企業のDX取組状況」、「DX実現に向けたITシステムへの対応」、「先端IT人材不足への対応」の観点から振り返っておきましょう。
企業のDX取組状況
『DX白書2023』によると、2021年と比較して2022年では日本企業全体においてDX推進に取り組む企業の割合は増加しています。
しかし、会社規模別に見ると、大企業は4割の企業がDX推進に取り組んでいるのに対し、潤沢な予算を確保しづらい中小企業ではDX推進に取り組んでいる企業の割合は全体の1割程度にとどまっています。このように、売上規模の大きな会社ほどDX推進に取り組んでいる割合が高くなる傾向があります。
ただし一方で、中小企業においてもデジタルを活用し業務改善や新たな事業創出を実現した事例も散見され始めており、企業の工夫や企業間の連携によって企業規模に関わらずDX推進を実現できる可能性も示唆されています。
➡︎【資料ダウンロード】さまざまな業界のDX推進事例をわかりやすく解説「DX事例集」<2025年版>
DX実現に向けたITシステムへの対応
レガシーシステム(老朽化した基幹システム)は企業のDX推進を阻む大きな障害です。しかし、日本企業のレガシーシステム刷新の現状は、「半分以上レガシーシステムが残っている」「ほとんどがレガシーシステムである」と答えた企業が全体の41.2%にものぼり、米国の22.8%に対して大きく遅れをとっています。
また、多くの企業でSaaS、クラウドなどの外部サービスやツールを導入する動きが進んでいる状況が見られるものの、変化の激しい市場のニーズに合わせた柔軟な事業変革を実現するために必要な「アジャイルの原則とアプローチ」をはじめとする新たな開発手法の活用はあまり活発に進んでいません。
➡︎【資料ダウンロード】ビジネスの変化に強い組織には「アジャイル」思考が必要不可欠!
先端IT人材不足への対応
DXを推進する人材の確保も日本企業全体における重要課題です。2021年に引き続き2022年においても、DX人材のニーズの高まりを受け、人材の「質」「量」双方において「大幅に不足している」と答えた企業が増加しています。
日本企業がDX人材の確保に苦戦している要因として、社員のリスキリング支援などのキャリア形成や学びに関する取り組みを実施していない企業の割合が高いことや、会社の求めるDX人材の設定および周知の不足、DX人材を想定した評価制度の整備がされていないことなどが挙げられます。
➡︎【資料ダウンロード】DX人材の定義・実態や必要スキルをわかりやすく解説
★その他、各業界のDX推進の現状や課題、成功事例などの詳細は下記のリンクをご覧ください
『DX動向2024』では成果を評価するためのPDCAが不十分と指摘
それでは今年発表された『DX動向2024』において、企業のDX状況はどのように評価されているでしょうか。
日本の企業全体としては前年対比でもDXの取組が年々増加していますが、サービス業や中小企業の取組状況は依然として遅れており、課題として捉える必要があるとしています。
DX の成果については、デジタイゼーション、デジタライゼーションの段階を踏んだ成果は出ているものの、デジタルトランスフォーメーションの段階での取組は成果が出ていない企業も多く、未だ途上との見方があります。
さらに、企業においてDXの取組内容ごとの成果を把握するための評価が十分に行われておらず、DX推進のPDCAサイクルが十分に形成されていないことが考えられると指摘しています。
★デジタイゼーション、デジタライゼーションについて詳しくはこちら
DX推進の進め方:5つのステップ
以上のポイントを踏まえた上で、一般的にDX推進とはどのように進められていくのでしょうか。0からDXを始める場合のステップを紹介します。ただし、ここで紹介しているのはあくまで一例です。本来、DX推進に決まった方法はなく、それぞれの会社の状況に合わせたさまざまなパターンが存在します。
➡︎【資料ダウンロード】さまざまな業界のDX推進事例をわかりやすく解説「DX事例集」<2025年版>
ステップ0:自社のDX推進度合いを認識する
まず、ステップ0として、そもそも自社のDX推進度合いを適切に把握する必要があります。
IPAのDX推進指標を活用し自己診断を行うことが可能です。
また、Webアンケート形式で約80の評価項目に回答すると、国内/海外の同業界などとの対比により自社のDX推進に対する強みや課題などの立ち位置を把握できることが可能なサービスもあります。
これは企業のDX推進度合いを客観的データに基づき把握することが可能となり、得られた結果を同一業界平均や国内トップ企業水準、グローバルトップ企業水準等と比較することで、自社の強みや課題を抽出し、将来的に強化すべき項目や企業の向かう方向性を見出すことができます。
★サービスについて詳しくはこちら
➡︎【資料ダウンロード】企業のDX成熟度を診断「DXケイパビリティ評価」
ステップ1:現状の可視化
DX推進を始める前に、まずは自社のビジネスや社内の現状を可視化することが重要です。例えば社内で使用している既存システムおよびその管理にかかっている人的リソース、部署ごとに管理している情報資産などを可視化します。
可視化作業が完了したら、現状の課題解決に向けてDX推進プロジェクトを担えるDX人材を確保しましょう。
➡︎【資料ダウンロード】企業のDX成熟度を診断「DXケイパビリティ評価」
ステップ2:人材確保と組織改革

現状の把握ができたら、次は社内の体制を整えるために人材確保や組織改革を実施しましょう。近年、DX推進プロジェクトを担える人材(DX人材)は企業競争力を高めるための重要な経営資源となりました。しかし、前述のように、日本企業のDX推進において事業戦略上の変革を担うDX人材は量・質ともに大幅に不足しているのが現状です。DX人材を確保するには、採用によって外部の人材を確保する方法と、既存社員のリスキリングやDX人材を育成して適切な人材を確保するという方法があります。
また、DX人材の確保が進まない要因には、単なる人手不足のみならず、企業の組織的な課題が原因となることもあります。例えば、DX推進を担う人材のスキル評価や処遇などのマネジメント制度の整備が進んでいない、自社のDX推進のために必要な人材の要件を明文化できていないといった組織の体制面で問題があります。社内制度を見直し、DX人材が適切な評価を受けられる環境を構築することも、人材の確保において重要なポイントです。
➡︎【資料ダウンロード】DX人材の定義・実態や必要スキルをわかりやすく解説
また、DX推進に適した組織体制の構築も重要なステップです。プロジェクトを進めるうえで社内の利害関係者の合意を得ることは不可欠ですが、DX推進には経営層のコミットが得られなかったり、各部署間の連携が築けなかったことが障壁となるケースがしばしば散見されます。
旧来のレガシーなシステムから脱却し、デジタル技術を活用した新たな業務フローやビジネスモデルへ移行するに際しては、経営層のコミットや十分な社内理解、各部署の協力関係が必要です。これを実現するためには、単なる組織構造の変革のみならず、組織の文化形成も重要なポイントとなります。組織の文化形成は後述の「DX推進のポイント:アジャイル文化形成の重要性」で詳しく解説します。
➡︎【資料ダウンロード】ビジネスの変化に強い組織には「アジャイル」思考が必要不可欠!
ステップ3:デジタルを活用した業務効率化
アナログ作業や手作業が多く発生している業務がある場合、SaaSや業務システム、ツールなどを導入してデジタイゼーションを推進していく必要があります。しかし、目先の業務を効率化するだけの目的で安易に外部サービスやツールを導入してしまうと、部署ごとの情報の分断を引き起こしてしまったり、複数のツールを契約することによる機能の重複やコスト増加などのリスクがあることも認識しておきましょう。
自社全体や外部環境、自社のビジネス成長を視野に入れて長期的な目線でプロセス全体を最適化していくという意識を持つことが重要です。
➡︎【資料ダウンロード】さまざまな業界のDX推進事例をわかりやすく解説「DX事例集」<2025年版>
ステップ4:データ活用の推進
不確実性の高い時代において環境の変化にいち早く対応するために、データに基づいた経営判断を実現する「データ利活用」「データドリブン経営」の重要性が高まっています。
しかし、データ利活用を適切に行えている企業は多くありません。「やみくもにデータだけを収集してしまい活用方法が見いだせない」「データ収集基盤そのものがない」などの課題を抱えた企業が大半です。まずは自社のデータ利活用レベルがどこに位置しているのかを適切に把握しましょう。
★あなたの組織のデータ利活用レベルは?簡単診断はこちら
また、データ利活用には、ユースケースから逆算して設計されたデータ収集基盤の構築が必要不可欠です。どのようにデータ収集基盤を設計すべきかは下記の記事で詳しく解説していますので、ご覧ください。
★データドリブン経営を実現させるには?詳しくはこちら
➡︎【資料ダウンロード】ビジネスにコミットする「データ利活用のガイドブック」
DX推進のポイント:アジャイル文化形成の重要性
DX推進では、目まぐるしく変化する時代のニーズや環境に合わせて柔軟にビジネスモデルや開発要件を変化させていくことが求められます。
これには従来通りのプロジェクトの進め方を続けていては対応できません。また、場当たり的に業務改善のためのツールやシステムを導入しただけでは他部門とのデータ連携やビジネスの変化に柔軟に対応できないリスクがあります。
激しい時代の変化や技術革新、ユーザーニーズの移り変わりに柔軟に対応するには「アジャイル」思考を組織にインストールしていく必要があります。
アジャイルはもともとソフトウェア開発手法の1つとして広まった用語で、アジャイル開発とは優先順位の高い要件から順に機能単位の小さなサイクルを繰り返す開発手法のことです。
★アジャイルについて詳しくはこちら
従来のウォーターフォール型の開発と比べて仕様変更に強く、プロダクトの価値を最大化することに重点を置いているのが特徴です。
アジャイルは、目まぐるしいビジネス環境の変化に柔軟に対応し続けることが求められるDX推進において、有効な思考法としても注目を集めています。近年では、会社組織の俊敏性を高めるために、アジャイルを単なる開発プロジェクトにとどまらず、組織形成においても導入しようとする企業が増えています。
★アジャイル組織について詳しくはこちら
➡︎【資料ダウンロード】ビジネスの変化に強い組織には「アジャイル」思考が必要不可欠!
企業のDX推進事例
モンスターラボは、デジタル領域の知見を活かし、企画・設計・デザイン・開発・運用の各段階から企業のDX推進戦略をあらゆる面からサポートしています。
ここではモンスターラボグループのDX推進サポート事例をもとに、企業のDX推進の取り組み・事例を紹介していきます。
AR診断アプリで建機故障時のダウンタイムを低減(クボタ)
建機・農機メーカーのクボタは、グローバル展開を図るなかで、海外の現地販売代理店の修理対応が担当者の経験・スキルによってばらつきがあることに課題を感じていました。
そこで同社は、販売代理店のサービスエンジニア向けに3Dモデル・ARを活用した故障診断アプリ「Kubota Diagnostics」を提供しました。
建機故障時の原因をビジュアルでスムーズに認識できるようになり、顧客側のダウンタイム削減に貢献。同時にカスタマーサポートの業務効率化を実現しました。また米国ユーザー向けのUI設計を実施し、現地ユーザーに受け入れられるローカライズにも成功しています。
★詳しくはこちら:
クボタ|故障診断アプリ『Kubota Diagnostics(クボタ ダイアグノスティックス)』
AIを活用した自動採寸アプリで事業コスト削減(ユニメイト)

レンタルユニフォーム事業や各種ユニフォームの企画・生産・販売やクリーニングまでを手がけるユニメイトでは、事業においてヒューマンエラーによるサイズ違いが頻発し、返品・交換に多大なコストが発生していることが大きな課題でした。
そこで同社は、AI画像認識を活用した自動採寸PWA「AI×R Tailor(エアテイラー)」を開発。サイズ測定対象者の背面・側面の写真と基本データ(身長・年齢・体重・性別)から適したサイズがフィードバックされる仕組みを構築しました。サイズ交換による自社・クライアント双方の作業負荷とコストの削減を実現し、返品や廃棄を少なくすることで環境保全にも貢献しています。
★詳しくはこちら:
ユニメイト|AIの画像認識を活用した自動採寸アプリ
注文フローのデジタル化によりコスト削減と顧客体験の向上を実現(Shake Shack)
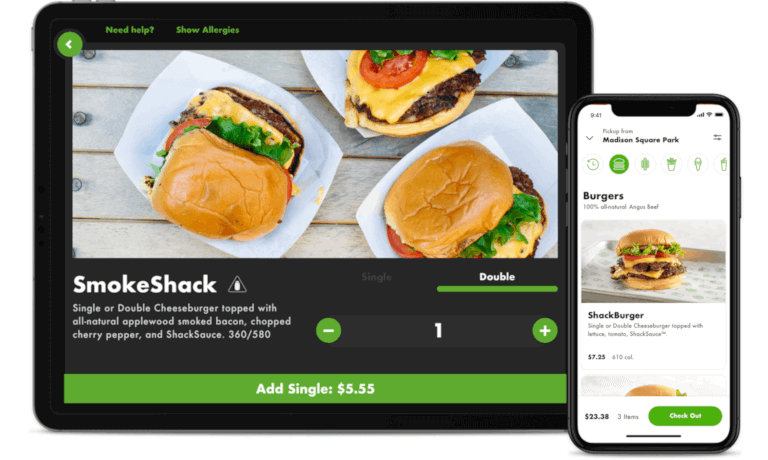
Shake Shack(シェイクシャック)は、ニューヨーク発のバーガースタンド。同社は、パーソナライズされた注文体験の提供を可能にする、レコメンド機能とプッシュ通知機能を搭載した事前注文アプリを開発。
モデルケースとして導入した店舗では、レジスタッフ分の人件費を削減できたうえに、注文フローのデジタル化により顧客単価が15%も増加。現在も継続的な改善を繰り返しながら、サービス拡大を目指しています。
★詳しくはこちら:
Shake Shack|オンライン注文プラットフォームの開発事例
アナログな仕入れ業務のペーパーレス化と業務効率化を実現(角上魚類)

手作業の仕入れ業務をデジタル化し、業界のフローを踏襲しながら業務効率化を実現
角上魚類ホールディングスは、主に関東地方・信越地方で鮮魚専門店「角上魚類」を展開する企業。同社は、手書きの受注明細やセリ原票を使用する仕入れ作業の負荷を改善するため『セリ原票アプリ』を開発。
市場特有の業務フローを崩さずデジタル化することで、手作業でのフローと遜色のない使い勝手を実現しただけでなく、リアルタイムでの情報連携も可能となったことでさらなる業務の利便性向上に寄与しました。
★詳しくはこちら:
角上魚類ホールディングス株式会社|手書き作業のデジタル化により、買い付け・配送業務を効率化『セリ原票アプリ』
企業のDX推進の取り組み事例についてより詳しく知りたい方は、国内外のさまざまな業界から厳選したDX成功事例を解説した下記の記事も参考にしてください。
➡︎【資料ダウンロード】さまざまな業界のDX推進事例をわかりやすく解説「DX事例集」<2025年版>
まとめ:DXはあらゆる企業にとっての最重要課題
DXについて解説してきましたが、いかがでしたか?
言葉の意味としてのDX(デジタルトランスフォーメーション)は、「進化したデジタル技術を浸透させることで人々の生活をより良いものへと変革する」というもの。
人間社会が豊かになる革新をもたらすポジティブなワードですが、ビジネス面では近い将来までに企業が解決すべき課題と認識されています。
移り行く時代の流れに取り残されてしまうのか、テクノロジーの進歩とともに新たな時代へと邁進していくのか、多くの企業にとっての分岐点になる取り組みともいえるでしょう。
とはいえ、経営層や現場責任者だけがいち早く注目したところで一朝一夕で片付けられるものではありません。自社の経営戦略をしっかりと固め、社内の理解・協力を得たうえで一丸となって取り組んでくことが大切です。
➡︎【資料ダウンロード】さまざまな業界のDX推進事例をわかりやすく解説「DX事例集」<2025年版>
Q
DX推進には、どのような人材が必要?
A
DX人材は、プロデューサー、ビジネスデザイナー、アーキテクト、データサイエンティスト、UXデザイナー、エンジニアの6つの職種に分けられます。詳しくはDX人材を解説した無料e-bookをご覧ください。
モンスターラボはDX推進を支援する伴走型パートナー
モンスターラボでは、世界各国のスペシャリストがチームを組み、さまざまな業界・業種のデジタルサービス/プロダクト開発から、UX/UIデザイン、ブランド開発、グロースハックまで幅広く支援しています。
ビジネスの上流工程からデジタル領域の知見を持つコンサルタントが中心となり、課題に合わせたソリューションを提案します。さらに、先端テクノロジーを含むあらゆるプラットフォームに対応できる開発体制を整えています。その他にも、アジャイル開発による柔軟な開発進行や、国内外のリソースを活用したスケーラブルな開発体制の構築、リリース後の保守運用や品質向上支援まで、さまざまなニーズに対応しています。
さらに、世界各国の拠点とネットワークを活かし、お客様のビジネスの海外展開も支援しています。対象地域におけるビジネス立案から現地調査まで、これまで培ったグローバルな支援実績をもとに伴走支援します。
モンスターラボが提供するサポートの詳しい概要は以下リンクをご確認ください。
DXに関連する注目トピックス
Monstarlab BlogではDXに関連したトレンド情報や注目トピックスを多数紹介しています。
ジェネレーティブAI(生成AI)
ジェネレーティブAIとは、与えられたデータをもとに画像や文章、コードといった新しいコンテンツを生成する技術のことです。生成AIとも呼ばれます。人間のようにクリエイティブなアウトプットを生み出せる点が従来のAIとは異なる点です。画期的な技術として注目を集め、さまざまな分野での活用が始まっています。
★詳しくはこちら
➡︎【5分でわかる】ChatGPTの導入ポイントと活用事例 <資料ダウンロード>
モダナイゼーション
モダナイゼーションは、レガシーシステムに蓄積された情報資産はそのまま活かし、システムのソフトウェアやハードウェアなどを新たなものへと置き換えることで、業務効率の向上やセキュリティ強化、グローバル化時代におけるビジネスの競争力強化などを目指します。
★詳しくはこちら
デザイン思考
デザイン思考(デザインシンキング)とは、デザイナーがデザインをおこなう際に用いられるプロセスを体系化したもの。ユーザー視点に立ってサービスやプロダクトの本質的な課題・ニーズを発見し、ビジネス上の課題を解決するための思考法として、注目されています。
★詳しくはこちら
UXデザイン
ユーザーの根本的なニーズに寄り添った“顧客体験を設計”するUXデザインは、製品やサービスの成功に欠かせない重要な要素として注目を集めています。
★詳しくはこちら
ベンダーロックイン
ベンダーロックインとは、ソフトウェアの機能改修やバージョンアップなど、導入したベンダー以外が実施できず、既存のベンダーを利用し続けないといけない状態になることです。同様に、ハードウェアのメンテナンスなどにおいても、他のベンダーに切り替えることが困難になってしまう状態のことを言います。
★詳しくはこちら
デジタルガバナンス・コード
デジタルガバナンス・コードとは、急速なデジタル化が拡大する市場・社会経済に対応するために、企業が実践すべき事柄をまとめたものです。経済産業省が策定しており、同省が推進しているDX(デジタルトランスフォーメーション)とも深く関わっているため、事業者や経営者にとっては非常に重要な会社経営の要素といえます。
★詳しくはこちら