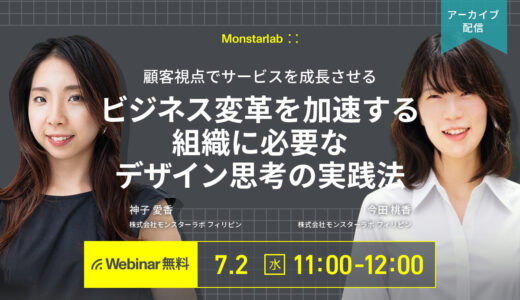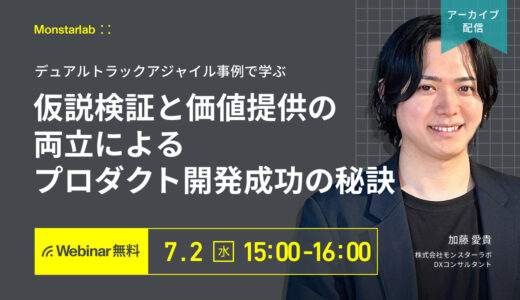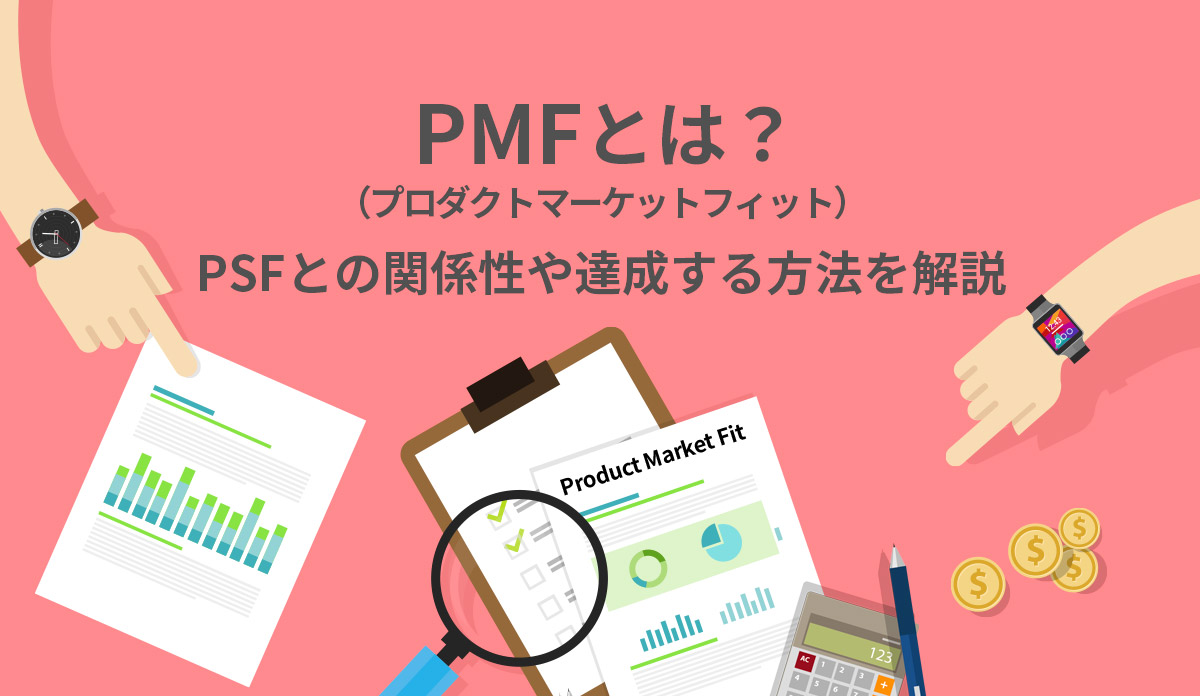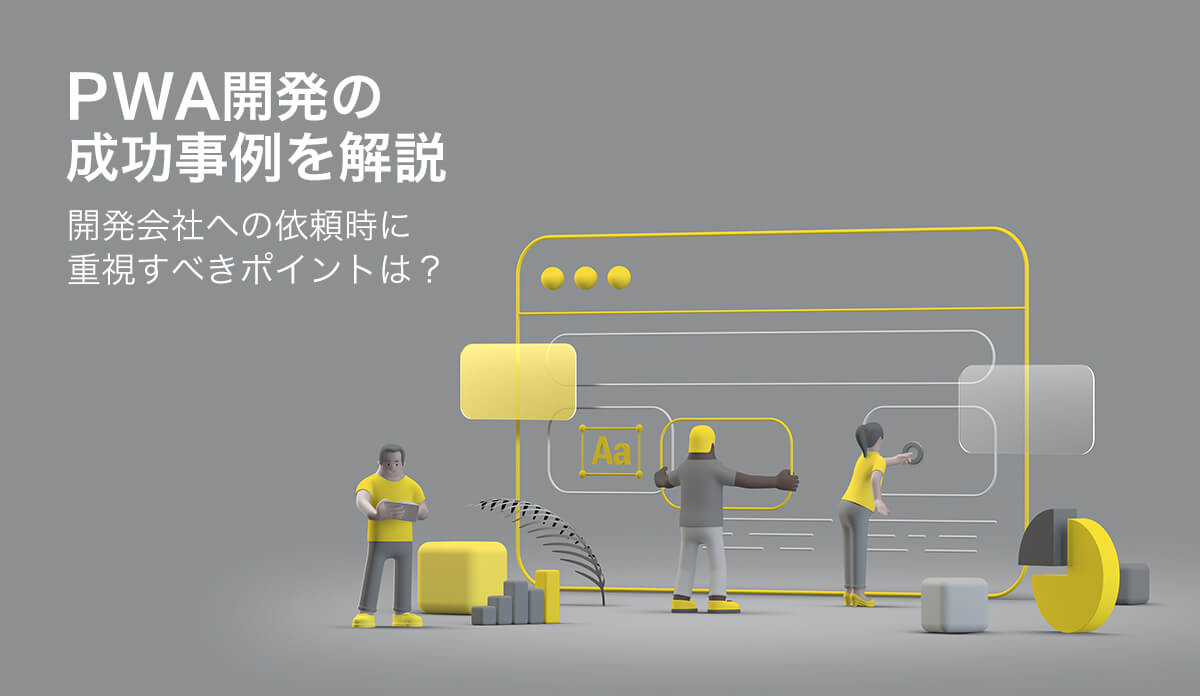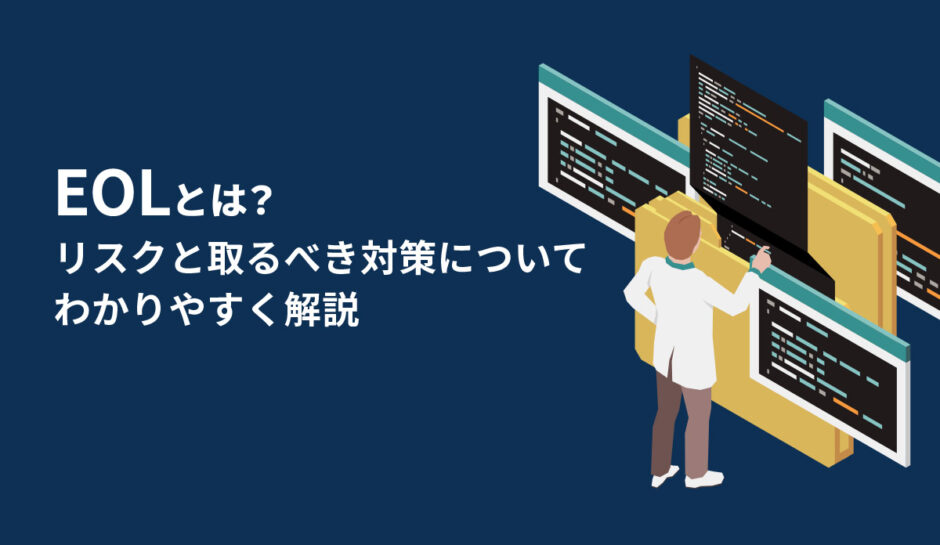
技術の進歩とともに到来する製品の寿命は、EOL(End of Life)と呼ばれます。
EOLは、ビジネスの継続性やセキュリティの観点から無視できない要素です。自社の製品のライフサイクルを把握し、EOLを迎える前に適切に対応しなければ、製品の保守や部品の調達が困難になり、自社のビジネスに支障をきたすおそれがあります。
EOLの内容とリスクを理解し、適切な対策を講じましょう。
➡︎【資料ダウンロード】ITモダナイゼーションを実現するステップとポイント<実践編>
目次
EOL(End of Life)とは?EOS、EOE、EOSLとの違い
EOL(End of Life)とは、製品のライフサイクルが終了することを意味します。「EOL」の関連用語には、製品の販売終了を意味する「EOS」、技術サポートの終了を意味する「EOE」、アフターサービスの終了を意味する「EOSL」などがあります。まずは、EOLの意味とこれら関連用語との相違点について解説します。
EOL(End of Life)とは?
EOLとは、製品のライフサイクルが終了し、メーカーによるサポートが打ち切られることを指します。ハードウェアであってもソフトウェアであっても、部品生産の停止やセキュリティ更新の提供終了などにより、製品の機能維持が困難になるタイミングが訪れます。企業が安定的にシステムを維持するためには、EOLを理解したうえで適切に対応しなくてはなりません。
EOS、EOE、EOSLとの違い
EOLに関連する用語として、EOS、EOE、EOSLなどが挙げられます。
EOS(End of Sales)は、販売終了を意味する言葉です。EOSを迎えたからといって直ちにサポートが打ち切られるわけではなく、一定期間はサポートが継続されます。
一方、EOE(End of Engineering)は、技術サポート終了を意味します。EOEを迎えると、バグの修正や機能改善が行われなくなります。
また、EOSL(End of Service Life)は、アフターサービスや保守といったサービスサポートの終了を意味します。
EOEもEOSLも、EOLとほぼ同じ意味を持ちますが、メーカーやシステムベンダーによって異なる用語が用いられています。
➡︎【資料ダウンロード】ITモダナイゼーションを実現するステップとポイント<実践編>
EOLが発生する理由
メーカーがEOLを設定する主な理由は、技術の進化や市場ニーズの変化に対応するため、そして製品の老朽化リスクを軽減するためです。
技術は常に進化しており、古い製品は最新の技術や規格に適合しにくくなります。
また、経年劣化による故障のリスクも高まります。したがって、メーカーが古い製品の保守や修理にリソースを投じ続けていると、技術の進化に遅れをとり、ニーズの変化に応じた製品を市場に届けることもできなくなります。
EOLを設定することで、メーカーは古い製品のサポートを終了し、新商品開発にリソースを集中させることができます。
EOL製品を使い続けるリスク
EOLを迎えた製品は、サポート終了により修理やトラブル対応ができなくなります。このため、EOL製品を使い続けると、サービス停止のリスク、セキュリティリスク、そして生産性低下のリスクを負うことになります。
サービス停止のリスク
EOLを迎えた製品は、メーカーによる修理対応やサポートが終了し、システム停止などのトラブルに対応してもらえなくなります。公式サポート以外の方法でサポートを受けられたとしても、修理・復旧に長時間を要したり、高額な費用が発生したりするおそれがあります。
ハードウェアの部品製造も終了するため、故障時の交換部品の入手が困難になります。また、ソフトウェアのアップデートがなされず老朽化すると、不安定な運用を強いられます。メーカーへの問い合わせもできず、保守対応も受けられません。
したがって、EOLを迎えた製品を使い続けていていると故障やトラブルの発生可能性が高まるうえ、復旧も難しく、業務の停滞を強いられることになります。
セキュリティリスク
EOLを迎えた製品は、セキュリティリスクが大幅に高まります。公式サポート終了にともないアップデートが停止されるため、新たに発見された脆弱性は修正されず、ハッキングやデータ漏洩の危険にさらされます。
とくに、OSやアプリケーションは、セキュリティホールが放置されたままとなり、攻撃対象になりやすい状態です。マルウェア感染のリスクも高まり、システム全体の機能停止や業務継続が困難になる可能性があります。
セキュリティ侵害は、企業の評判失墜、顧客離れ、法的責任など、深刻な影響をもたらします。EOL製品を使い続ける最大のリスクのひとつといえるでしょう。
生産性低下のリスク
EOLを迎えたシステムには、アップデートが提供されなくなります。このため、互換性の問題が発生しやすくなります。新たなシステムやソフトウェアとの連携が困難になり、パフォーマンス低下や操作性の悪化を招きます。これは、業務効率の低下に直結し、長期的には大きなコスト増につながる可能性があります。
さらに、EOL製品は公式サポートが終了するため、障害発生時の対応は自社責任となります。専門家のサポートを受けられないため、迅速な復旧が難しく、生産性が低下するばかりか、事業の継続性にも大きな影響を与えかねません。
➡︎【資料ダウンロード】ITモダナイゼーションを実現するステップとポイント<実践編>
EOLへの対策
EOLへの対策としては、製品情報の整理とリプレイス計画が重要です。まずは自社システムを棚卸し、使用中の製品情報を正確に把握したうえで、EOLのスケジュールを確認します。計画とあわせて、最適な見積もりに基づく予算を確保しておきましょう。また、企業によっては、第三者保守サービスの利用やクラウドへの移行、オープンソースソフトウェア(OSS)の採用も有効な対策になります。
製品ごとのEOL情報の整理
まず、自社システムの棚卸を行い、使用中のハードウェア、ソフトウェア、OS、アプリケーションを全て洗い出します。各製品のメーカー、型番、バージョンなどを正確に把握し、資産台帳やインベントリ管理システムに登録しましょう。従業員が無断で使用しているツールがないかどうかも確認しておきましょう。
次に、各メーカーのWebサイトや公式ドキュメントを参照し、EOLのスケジュールを確認します。製品ごとにサポート終了日を把握したら、カレンダーなどに登録してリマインダーを設定することで、見落としを防げます。
リプレイスの計画
EOLが近い製品は、代替製品への移行計画を早期に策定しましょう。EOLにともなうシステム停止やセキュリティリスクを回避するには、事前のリプレイス計画が重要です。
まず、自社のシステム構成に基づき、新システムへの移行計画を策定します。既存のアプリケーションやソフトウェアへの影響、互換性の問題などを洗い出し、対策を講じます。あわせて、リプレイス後の動作検証に向けた計画も立てておきます。動作検証の工程では、社内のエンドユーザーを巻き込み、パイロットグループによる検証も計画しましょう。
リプレイス計画には、費用と日程に加え、製品の入荷予定も組み込みます。メーカーやサプライヤーと調整し、納期遅延へのバックアップ計画も用意しておくと安心です。
計画確定後は、社内に作業内容とスケジュールを明確に伝え、従業員の協力が得られる体制を整えます。早期に計画を策定しておくことで、予算確保やリプレイス作業を円滑に進めることができます。
リプレイス費用の確保
EOLにともなうシステムのリプレイスには、事前に費用を見積もり、予算を確保しておくことが不可欠です。
見積もりには、機器の購入費に加え、システム設計、構築、テスト、データ移行、トレーニングといった作業にかかる費用も含まれます。また、外部業者に委託する場合、それらの費用も計上します。
予算は、機器の規模や複雑さ、データ量、作業工数によって大きく変動します。相見積もりを取得し、費用対効果を比較検討することで、最適な予算を固めましょう。
企業の予算は通常、年度単位で決定されるため、リプレイス決定後すぐに予算が確保できるとは限りません。EOLのスケジュールを考慮し、余裕を持って予算見積もりを作成し、稟議で承認を得ることが重要です。
さらに、予期せぬトラブル発生時の対応費用も考慮し、予算にバッファを設けておきましょう。これにより、不測の事態にも柔軟に対応できます。
第三者保守サービスの利用
EOL製品を継続利用する際の有効策として、第三者保守サービスの活用が挙げられます。第三者保守ベンダーは、メーカーサポート終了後の製品に対し、独自の保守体制と部品調達ルートを駆使してサポートを提供します。不具合発生時の対応はもちろん、予防保守やセキュリティ対策にも対応できます。
第三者保守のメリットは、柔軟にカスタマイズできる点にあります。24時間365日対応や特定機器限定の契約など、自社システムに最適なプランを構築できます。複数メーカーの機器を一括して保守を依頼することで、窓口の一本化による運用管理の効率化とコスト削減も期待できるでしょう。
クラウドサービスへの移行
EOL問題の抜本的な解決策として、クラウドサービスへの移行が挙げられます。
クラウドサービスは、常に最新のセキュリティ対策とアップデートが提供されるため、EOLへの懸念が大幅に軽減されます。また、スケーラビリティや柔軟性の向上、長期的なコスト削減効果も見込めます。
EOLリスクを最小限に抑え、円滑なシステム運用を継続するためにも、クラウド移行を検討してみてはいかがでしょうか。
オープンソースソフトウェアの採用
EOL対策のひとつとして、プロプライエタリソフトウェアをオープンソースソフトウェア(OSS)の代替品に移行する方法があります。
OSSは、大規模なコミュニティによって開発・サポートされているため、特定ベンダーのEOLポリシーに縛られることなく利用できます。OSSの具体例としては、Microsoft OfficeからLibreOfficeへ、商用データベースのOracleやSQL ServerからPostgreSQLへ、商用CMSからWordPressへ、といった置き換え例が挙げられます。
OSSを採用することでコストを削減できる一方で、サポート体制の構築やセキュリティ管理は自社で行わなくてはなりません。そのため、自社に十分なリソースと専門知識をもつ人材が必要です。OSSの導入を検討する際は、これらの点を考慮し、自社システムへの適合性を慎重に評価しましょう。
➡︎【資料ダウンロード】ITモダナイゼーションを実現するステップとポイント<実践編>
まとめ:自社製品のEOLを把握してリスクに備えよう!
製品のライフサイクルの終了を意味するEOLを迎えると、メーカーやベンダーによるサポートが停止し、機器やシステムの修理不能や高額な費用負担、脆弱性放置によるセキュリティ侵害、業務効率低下といったリスクが発生します。
このため、自社のEOL製品に関する情報を整理し、あらかじめリプレイス計画を策定し、費用を確保しておく必要があります。また、第三者保守サービスの利用やクラウドサービスへの移行、オープンソースソフトウェアの採用を検討することも有効な対策となるでしょう。自社の機器やシステムのEOLを把握したうえで、EOLにともなうリスクに備えましょう。
➡︎【資料ダウンロード】ITモダナイゼーションを実現するステップとポイント<実践編>
サービス・プロダクト開発を検討している企業ご担当者様へ
モンスターラボは、約20年にわたるサービス・プロダクト開発実績から得られたデジタル領域の知見や技術力を活かし、デジタルプロダクト開発事業を展開しています。
先端テクノロジーに対応した高度なIT人材があらゆるプラットフォーム上での開発を支援します。アジャイル開発とDevOpsによる柔軟な開発進行や、国内外のリソースを活用したスケーラブルな開発体制の構築も可能です。 また、リリース後の保守運用や品質向上支援まで伴走可能です。
モンスターラボが提供するサポートの詳しい概要は以下リンクをご確認ください。